相続時の節税に使える控除制度と計算方法まで徹底解説
- 相続税コラム
- 最終更新日:
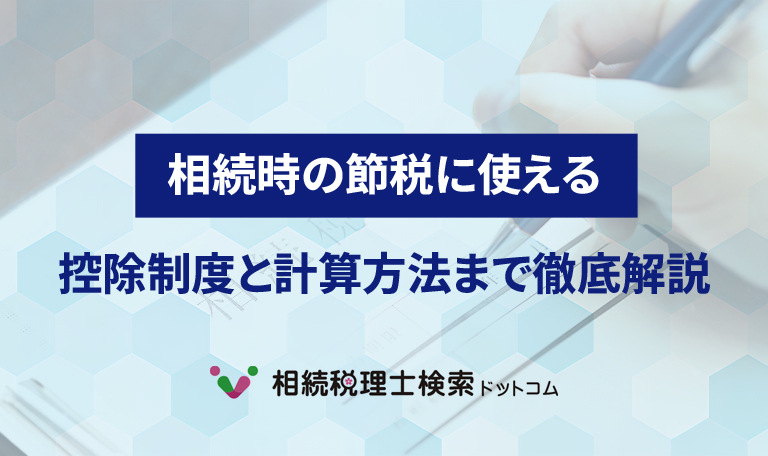
相続税の負担を少しでも軽くしたいというのは、相続を受ける側、相続する側、双方の課題です。相続税には「基礎控除」や「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」など、活用できる制度が数多く用意されています。これらは相続人や遺産の状況に応じて適用できるかどうか、また、控除額が変わるため、仕組みを理解しておくことが重要です。『こういった控除があるんだ』と知っておくだけでも、いざとなった時に思い返すこともできます。
本記事では相続時の節税に使える控除制度を解説します。
目次
知っておきたい控除制度は『9つ』
相続税の申告で主に利用される控除制度として以下の9つがあります。
- 基礎控除
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 贈与税額控除
- 小規模宅地等の特例
- 生命保険金の非課税枠
- 退職手当金の非課税枠
それぞれの控除制度の該当要件や控除額の計算方法を、以下にまとめます。
①基礎控除
基礎控除は相続税を計算する際に、必ず使用する制度です。
すべての相続人に共通して差し引かれる金額を『基礎控除』といいます。
この基礎控除では、一定額まで相続税がかからないという仕組みがあります。
基礎控除の計算方法を解説
基礎控除の金額は、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹など『法定相続人の人数』によって決まります。
計算式は以下です。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば遺産総額が5,000万円、法定相続人数は2人としましょう。この場合は以下のようになります。
(例)基礎控除の算定
3,000万円+(600万円×2人) = A.4,200万円
(例)対象になる相続税額
5,000万円 – 4,200万円 = A.800万円
相続財産の総額5,000万円と控除額4,200万円との差額の800万円に対して相続税がかかります。
人数というのが鍵で、『相続人の人数が増えれば基礎控除額は大きくなり、お得になる』と言えます。
②配偶者控除
数多くある控除の中でも、最も負担軽減が大きい控除で、1億6,000万円、配偶者の法定相続分に相当する額のいずれかの金額の大きい額までが配偶者控除の対象となります。
この配偶者控除を使用するには以下のような適用要件があります。
配偶者控除の適用要件
戸籍上の正式な配偶者であること
内縁関係や事実婚の場合は対象にはなり得ません。
相続税の申告を行うこと
基礎控除内で相続税がゼロの場合を除き、配偶者控除を受けるためには相続税申告が必須です。申告書に「配偶者控除を適用する旨」を記載し、必要な添付書類を提出する必要があります。
期限内での申告を行うこと
相続発生日から10か月以内に相続税の申告・納付を完了させる必要があります。
③未成年者控除
未成年者控除は相続人が未成年者(20歳未満)の場合に適用される相続税の税額控除制度です。
未成年で社会的・経済的に自立することが難しいことを考慮して、負担を軽減する目的で設けられています。
未成年者控除の計算方法を解説
法改正後(令和4年4月1日以後)のルールで解説します。
法定相続人が18歳未満の場合、その相続人が18歳に達するまでの年数(1年未満は切り上げ)×10万円 を計算し、その金額を相続税額から控除できます。
計算式は以下です。
未成年者控除=(18歳 − 相続開始時の年齢)×10万円
(例)未成年者控除の算定例
15歳9ヶ月で相続開始した場合を例に計算します。
年齢を差し引いた時に1年に満たない場合は切り上げになります。
(18歳−15歳(9ヶ月))=2年3ヶ月→切り上げて3年に
3年×10万円 = A.30万円
上記のようになります。
④障害者控除
相続人が障害者である場合などは生活や就労に制限があることを考慮し、相続税の負担を軽減するために「障害者控除」という制度が設けられています。
障害者控除の計算方法を解説
85歳を基準とし、相続開始時の年齢を差し引いた年数(1年未満は切り上げ)×10万円 を計算し、その金額を相続税額から控除できます。
計算式は以下です。
控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円もしくは20万円*
*一般障害者の場合は10万円、特別障害者の場合は20万円
(例)未成年者控除の算定例
50歳9ヶ月で相続開始した場合を例に計算します。
年齢を差し引いた時に1年に満たない場合は切り上げになります。
(85歳−50歳(9ヶ月))=34年3ヶ月→切り上げて35年に
35年×10万円 = A.350万円
上記のようになります。
⑤相次相続控除
前回の相続の発生から10年以内に続けて相続が発生した場合に使える控除制度です。
同じ財産に対して短期間で二重に相続税が課せられてしまうため、その負担を調整するために設けられているのが『相次相続控除』です。
相次相続控除の計算方法を解説
10年から経過年数を差し引いて、前回の相続税額をかけて、10で割ります。
以下のような計算式になります。
相次相続控除=1回目の相続税額×(10年-経過年数)÷10
(例)相次相続控除の算定例
1回目の相続で納めた税額が500万円、5年後に2回目の相続が発生した場合は以下のようになります。
500万円×(10年-5年)÷10 = A.250万円
二回目の相続税から250万円が差し引けます。
⑥贈与税額控除
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合に適用できる制度です。
贈与を受けた財産は当然、相続財産に加算されて課税対象になりますが、その際にすでに納めた贈与税を相続税から差し引くことができるようになっています。これに制度は、同じ財産に対して二重に課税されることを防ぐことを目的としています。
相次相続控除の計算方法を解説
相続税額 + 相続開始の3年前に受けた贈与額から算定された相続税額から、贈与税としてすでに納税済み額が引かれます。
⑦小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた土地や事業用に使っていた土地の、一定の面積まで相続税評価額を大幅に減額できる制度が『小規模宅地等の特例』です。
土地は相続財産の中でも評価額が大きくなりやすく、相続税の負担になるため、この特例は節税の中でも重要な役割を持っています。
減額の対象とは?
- 被相続人が住んでいた土地(居住用宅地)の場合は最大330㎡まで80%減額
- 被相続人が営んでいた事業に使っていた土地(事業用宅地)の場合は最大400㎡まで80%減額
- 被相続人がマンションなどの賃貸事業に使っていた土地(貸付事業用宅地)の場合は最大200㎡まで50%減額
小規模宅地等の特例の適用要件
- 相続人がその土地を相続し、一定の要件を満たして利用を継続する
- 居住用の場合は、配偶者、同居の親族、あるいは相続開始前から持ち家を持たずに居住していた親族。
- 相続税の申告手続きと、それに必要な書類を提出して適用を受ける手続きを行う
⑧生命保険金の非課税枠
相続財産として受け取った生命保険金には、一定額まで相続税がかからない非課税枠が設けられています。ご遺族の生活保障を目的とした制度で、現金で受け取れる保険金に非課税枠を設け、相続税の負担を軽減する仕組みです。
生命保険金の非課税枠の計算方法を解説
計算方法は単純です。
生命保険金の非課税枠=500万円×相続人数
(例)生命保険金の非課税枠の算定例
保険金が3,000万円で、相続人が3人場合は以下のようになります。
500万円×3人=1,500万円
3,000万円の保険金に対して非課税額が1,500万円あるため、課税は1,500万円に対してのみ行われます。
⑨退職手当金の非課税枠
被相続人が亡くなった際に、勤務先から遺族へ支払われる退職手などの死亡退職金を受け取った場合に、一定額まで相続税がかからない非課税枠が設けられています。
退職手当金の非課税枠の計算方法を解説
計算方法は生命保険金の非課税枠と同様です。
退職手当金の非課税枠=500万円×相続人数
(例)退職手当金の非課税枠の算定例
退職手当金が3,000万円で、相続人が3人場合は以下のようになります。
500万円×3人=1,500万円
3,000万円の保険金に対して非課税額が1,500万円あるため、課税は1,500万円に対してのみ行われます。
相続税は意外に縮小できる
上記の9つの控除制度を利用すれば実は相続税の負担は大幅に圧縮できることがわかります。基礎控除や配偶者控除、小規模宅地等の特例、生命保険金や退職金の非課税枠など、状況に応じて適用できる制度は多岐にわたりますが制度の内容を正しく理解し、計画的に活用することが重要です。
まとめ
相続税の節税には、法律で認められた控除制度を最大限に活用することが不可欠です。基礎控除や配偶者控除は広く適用される一方、小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠などは条件次第で効果が大きく変わります。これらを適切に組み合わせることで、相続税の負担を大幅に圧縮できる可能性があります。ただし、手続きや必要書類の準備には専門家にサポートを受けながら行うことをおすすめします。
